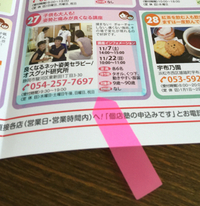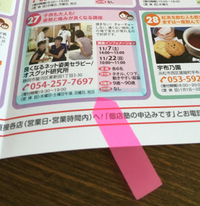2009年12月17日
わたしが考える介護予防について、
ある程度、身体を動かせることができれば、寝たきりのひとでも立ち上がることができます。
90歳以上も可能です。
指が動く、ここからはじめる。でも十分可能です。
手が動かさせることができれば、なお良くなる範囲は広くなります。
腕が動く!
足が痛いけど、動かせる。
そこまで、動かすことができるのなら、
だいじょうぶ、
かなならず良くなるんですよ。
ようは、あきらめない。
動かないことに目を向けるのでなく、動くことのほうに重点を置く。
そして、より動かせるように、すれば、よい。
無理に動かない状態をひっぱったり、動かすのは、身体機能と脳の反応からすると、逆効果。
痛いという状態で、横になって休んでも、寝ても
もとには戻りません。
原因と、おかしくなった要因はかならずあります。
大方、検査での数値で、わからない。という方の場合は、原因不明で迷路に入ります。
迷路に入る前に、一度自分の状態を知るということは、試しても良いのではないか。
家族で、高齢になったひとがいる。
大切とおもい、できることを取り上げて、なにもさせない。
どこが、わるくなり、動けないということで、ただ寝かせている。
そして、手に負えないとなると、
施設へ依存する。(送る)
そんなことでよいのか???疑問でいっぱいである。
本人が、自力でできることを取り上げないで、可能な限りできることを、よりよくさせる。
農作業をさせたりさせて、八百屋へ楽しく買い物させて、
ひとりでも、早くこのことに気がついてほしいと願うばかりです。
ここ数年、伝える努力を怠っていました。(反省)
------これは同意できる---------
「まず生活を知ってから医療に入るべきだと思う。
そのためには自宅を訪問するのがいい。
食事や寝室、家族関係など患者を取り巻くいろんな状況が一目で分かる。
人の生活の中で、医療はちょっとした助っ人に過ぎない。
主役はその人なのに、いったん患者になると、
途端に医師が主役に変わるのはおかしなこと。
----------------
同意理由
人は生活動線の中で、体を使うからです。
そして、静的動作で負担を感じ、その状態を記憶するからです。

90歳以上も可能です。
指が動く、ここからはじめる。でも十分可能です。
手が動かさせることができれば、なお良くなる範囲は広くなります。
腕が動く!
足が痛いけど、動かせる。
そこまで、動かすことができるのなら、
だいじょうぶ、
かなならず良くなるんですよ。
ようは、あきらめない。
動かないことに目を向けるのでなく、動くことのほうに重点を置く。
そして、より動かせるように、すれば、よい。
無理に動かない状態をひっぱったり、動かすのは、身体機能と脳の反応からすると、逆効果。
痛いという状態で、横になって休んでも、寝ても
もとには戻りません。
原因と、おかしくなった要因はかならずあります。
大方、検査での数値で、わからない。という方の場合は、原因不明で迷路に入ります。
迷路に入る前に、一度自分の状態を知るということは、試しても良いのではないか。
家族で、高齢になったひとがいる。
大切とおもい、できることを取り上げて、なにもさせない。
どこが、わるくなり、動けないということで、ただ寝かせている。
そして、手に負えないとなると、
施設へ依存する。(送る)
そんなことでよいのか???疑問でいっぱいである。
本人が、自力でできることを取り上げないで、可能な限りできることを、よりよくさせる。
農作業をさせたりさせて、八百屋へ楽しく買い物させて、
ひとりでも、早くこのことに気がついてほしいと願うばかりです。
ここ数年、伝える努力を怠っていました。(反省)
------これは同意できる---------
「まず生活を知ってから医療に入るべきだと思う。
そのためには自宅を訪問するのがいい。
食事や寝室、家族関係など患者を取り巻くいろんな状況が一目で分かる。
人の生活の中で、医療はちょっとした助っ人に過ぎない。
主役はその人なのに、いったん患者になると、
途端に医師が主役に変わるのはおかしなこと。
----------------
同意理由
人は生活動線の中で、体を使うからです。
そして、静的動作で負担を感じ、その状態を記憶するからです。
◇◇今回の投稿は、下記の記事を読んで思ったことでした。◇◇
●長野で”先進”地域医療 色平哲郎さんに聞く
威厳捨て患者に寄り添う まず訪問し生活知る
日本経済新聞 09年12月10日(木)夕刊
=村人と酒を酌み交わし、祭りや葬式、道の補修に飛び込んだ=
長野県は住民が長命。
しかも1人当たり老人医療費が全国一安いと評価されてきた。
医師と看護師が自宅訪問や予防に力を入れ、
「長野モデル」といわれる地域医療を確立させたからだ。
先頭に立つ佐久総合病院(佐久市)は山間の診療所にも医師を派遣、
その一つが南相木村(みなみあいきむら)にある。
「初めて南相木村に来た時、江戸期の感覚が残っていると感じた。
自分の生き方を自分で決める、
そんなどっしり構えた”野性の”老人たちに会え、学ぶことが多かった」
同村は人口1100人、高齢化率は40%近い無医村だった。
色平哲郎さんは診療所長として家族5人で移り住み、昨春まで10年間暮らした。
自宅の電話番号を公開していつでも診療に応じ、患者宅を気楽に訪ねた。
「村人は年老いても、自分でできることは人のために
やってあげたいと常に思っている。
拝金主義やテレビ情報に振り回されない立ち居振る舞いがあった。
医師はそんな自律した村人と寄り添えばいい。
都会では得られない醍醐味(だいごみ)です」
高度成長を経て都会では消えた
「お互いさま、おかげさまで」の支え合いの世界である。
妻の嘉須美さんは若妻会に入り、色平さんはその義父母を診察する。
夫婦で情報交換し、村社会独特の襞(ひだ)に納得する。
「村では身内とよそ者をまず分けるのですが、
だんだん身内になってきたと思う」
住民の気持ちを伝えてくれた案内人にも恵まれた。
前任の南相木村診療所で出会ったベテランの女性保健師である。
性急に事を運んではならないと言われた。
「村の人に言いたいことがあっても、まず10分の1にすること。
そして10回通えばいい、と教わった。
(院長の)若月俊一先生が話していた『民衆には3歩では早過ぎる。
1歩前へ』と同じだと思った」
若月院長は1945年に東京から現在の佐久総合病院に赴任。
農村医学を唱え、地域医療に生涯を捧(ささ)げた。
76年にマグサイサイ賞を受賞。
同病院の中庭に銅像が建つ。
「例えば、診察に来たばあちゃんが気になるので自宅に行く。
いきなりその家の戸口に白衣で現れたら、ばあちゃんは驚いてしまう。
なぜ来たかと聞かれたら、紅葉がきれいなので眺めていたと話す。
そこから世間話を始める。
もちろん白衣なんか着ない。
お茶を頂き、気安い関係になると、実は、とやっと体調の話をしてくれる」
「医師の威厳」をいったん脱ぎ捨てる。
日々の活動が医療への疑問につながった。
=人の暮らしを丸ごと受け止めていきたい=
広辞苑で、医療は「医術で病気をなおすこと」とある。
医学界では「医学の社会的適用」とよくいわれる。
「だいぶ違うと思う。
広辞苑の定義に『患者に寄り添うこと』と加えたい。
これはケア(介護)だと見られがちだが、実はキュア(治療)とケアは語源が同じ。
ラテン語のクーラです。
うなだれた戦士の内面のことで、彼の憂いを共有する気持ちも含まれる」
心身が傷ついた状態を目の前にして、
それにかかわろうという姿勢が医療や介護の基本だと言う。
「相手のつらさをまず受け止め、人間として人間の世話をすることなのです。
気にかける、心配する、あるいは他人の幸せを準備するということです。
一言で言えば、配慮ある見守り。
南相木村にはこういう心がありましたね」
「人間としてのケアは、医師が特権化されるはるか前から実践されてきた。
その治療に関する技術的な部分が医学・医療としてすくいあげられたにすぎない」
医療の原点を知ったのが、フィリピンでの衝撃体験だった。
医学生として、バングラデシュ出身の保健師の地域実習に同行。
「石鹸(せっけん)の代わりになる草を教え、
下痢をした患者にはスープの作り方を指導する。
すぐに役立つ医療的な知識を住民に次々与えていった。
だけど、僕には何も分からない。
大学で教わってきた医療ではない、人の世話をする人としての姿勢に気付かされた。
本当に驚いた」
その5歳年上の保健師、スマナ・バルアさんは医師となり、今、
世界保健機関(WHO)に所属、アジア各国を飛び回っている。
=介護職とチームを組んだゼロ次医療の普及を=
「病院から来ました」と、玄関先で明るく声をかけて患者の自宅を回る色平さん。
南相木村診療所から佐久総合病院に移り、佐久市内を担当している。
患者の体を触りながら「ここが痛みますか」と尋ね、見守る家族から近況を聞き出す。
「まず生活を知ってから医療に入るべきだと思う。
そのためには自宅を訪問するのがいい。
食事や寝室、家族関係など患者を取り巻くいろんな状況が一目で分かる。
人の生活の中で、医療はちょっとした助っ人に過ぎない。
主役はその人なのに、いったん患者になると、
途端に医師が主役に変わるのはおかしなこと。
地域医療とは、医療の一分野というより地域の一役割です」
健康な人にも普段のかかわりが大事だという。
診療所や訪問診療が1次医療で地域の拠点病院は2次医療、
大学病院など高度医療が3次医療。
もう一つ、健康な人への保健・予防活動、
すなわちゼロ次医療が欠かせないと話す。
「そもそも人の幸せとは何だろうか。
僕は、好きな人と好きな場所で暮らすことだと思う。
それを中心になって支えるのは、医師というより看護と介護。
保健師、訪問看護師と介護職の連携が必須。
医療と福祉の垣根を取り払い、チームで取り組むべきでしょう。
特権化した高度医療志向の医師たちを、
チームで担う地域医療に振り向けるような政策を期待したい」
(編集委員 浅川澄一)
いろひら・てつろう
医師。1960年横浜市生まれ。東大工学部を中退、世界を放浪。
83年京大医学部入学、90年卒業。96年JA長野厚生連に入り、
長野県南牧村の診療所長、98年同県南相木村診療所長。
2008年4月佐久総合病院地域ケア科に移り、現在同科医長。
著書に「大往生の条件」「源流の発想」など。
シニア記者がつくるこころのページ (毎週木曜に掲載)
●長野で”先進”地域医療 色平哲郎さんに聞く
威厳捨て患者に寄り添う まず訪問し生活知る
日本経済新聞 09年12月10日(木)夕刊
=村人と酒を酌み交わし、祭りや葬式、道の補修に飛び込んだ=
長野県は住民が長命。
しかも1人当たり老人医療費が全国一安いと評価されてきた。
医師と看護師が自宅訪問や予防に力を入れ、
「長野モデル」といわれる地域医療を確立させたからだ。
先頭に立つ佐久総合病院(佐久市)は山間の診療所にも医師を派遣、
その一つが南相木村(みなみあいきむら)にある。
「初めて南相木村に来た時、江戸期の感覚が残っていると感じた。
自分の生き方を自分で決める、
そんなどっしり構えた”野性の”老人たちに会え、学ぶことが多かった」
同村は人口1100人、高齢化率は40%近い無医村だった。
色平哲郎さんは診療所長として家族5人で移り住み、昨春まで10年間暮らした。
自宅の電話番号を公開していつでも診療に応じ、患者宅を気楽に訪ねた。
「村人は年老いても、自分でできることは人のために
やってあげたいと常に思っている。
拝金主義やテレビ情報に振り回されない立ち居振る舞いがあった。
医師はそんな自律した村人と寄り添えばいい。
都会では得られない醍醐味(だいごみ)です」
高度成長を経て都会では消えた
「お互いさま、おかげさまで」の支え合いの世界である。
妻の嘉須美さんは若妻会に入り、色平さんはその義父母を診察する。
夫婦で情報交換し、村社会独特の襞(ひだ)に納得する。
「村では身内とよそ者をまず分けるのですが、
だんだん身内になってきたと思う」
住民の気持ちを伝えてくれた案内人にも恵まれた。
前任の南相木村診療所で出会ったベテランの女性保健師である。
性急に事を運んではならないと言われた。
「村の人に言いたいことがあっても、まず10分の1にすること。
そして10回通えばいい、と教わった。
(院長の)若月俊一先生が話していた『民衆には3歩では早過ぎる。
1歩前へ』と同じだと思った」
若月院長は1945年に東京から現在の佐久総合病院に赴任。
農村医学を唱え、地域医療に生涯を捧(ささ)げた。
76年にマグサイサイ賞を受賞。
同病院の中庭に銅像が建つ。
「例えば、診察に来たばあちゃんが気になるので自宅に行く。
いきなりその家の戸口に白衣で現れたら、ばあちゃんは驚いてしまう。
なぜ来たかと聞かれたら、紅葉がきれいなので眺めていたと話す。
そこから世間話を始める。
もちろん白衣なんか着ない。
お茶を頂き、気安い関係になると、実は、とやっと体調の話をしてくれる」
「医師の威厳」をいったん脱ぎ捨てる。
日々の活動が医療への疑問につながった。
=人の暮らしを丸ごと受け止めていきたい=
広辞苑で、医療は「医術で病気をなおすこと」とある。
医学界では「医学の社会的適用」とよくいわれる。
「だいぶ違うと思う。
広辞苑の定義に『患者に寄り添うこと』と加えたい。
これはケア(介護)だと見られがちだが、実はキュア(治療)とケアは語源が同じ。
ラテン語のクーラです。
うなだれた戦士の内面のことで、彼の憂いを共有する気持ちも含まれる」
心身が傷ついた状態を目の前にして、
それにかかわろうという姿勢が医療や介護の基本だと言う。
「相手のつらさをまず受け止め、人間として人間の世話をすることなのです。
気にかける、心配する、あるいは他人の幸せを準備するということです。
一言で言えば、配慮ある見守り。
南相木村にはこういう心がありましたね」
「人間としてのケアは、医師が特権化されるはるか前から実践されてきた。
その治療に関する技術的な部分が医学・医療としてすくいあげられたにすぎない」
医療の原点を知ったのが、フィリピンでの衝撃体験だった。
医学生として、バングラデシュ出身の保健師の地域実習に同行。
「石鹸(せっけん)の代わりになる草を教え、
下痢をした患者にはスープの作り方を指導する。
すぐに役立つ医療的な知識を住民に次々与えていった。
だけど、僕には何も分からない。
大学で教わってきた医療ではない、人の世話をする人としての姿勢に気付かされた。
本当に驚いた」
その5歳年上の保健師、スマナ・バルアさんは医師となり、今、
世界保健機関(WHO)に所属、アジア各国を飛び回っている。
=介護職とチームを組んだゼロ次医療の普及を=
「病院から来ました」と、玄関先で明るく声をかけて患者の自宅を回る色平さん。
南相木村診療所から佐久総合病院に移り、佐久市内を担当している。
患者の体を触りながら「ここが痛みますか」と尋ね、見守る家族から近況を聞き出す。
「まず生活を知ってから医療に入るべきだと思う。
そのためには自宅を訪問するのがいい。
食事や寝室、家族関係など患者を取り巻くいろんな状況が一目で分かる。
人の生活の中で、医療はちょっとした助っ人に過ぎない。
主役はその人なのに、いったん患者になると、
途端に医師が主役に変わるのはおかしなこと。
地域医療とは、医療の一分野というより地域の一役割です」
健康な人にも普段のかかわりが大事だという。
診療所や訪問診療が1次医療で地域の拠点病院は2次医療、
大学病院など高度医療が3次医療。
もう一つ、健康な人への保健・予防活動、
すなわちゼロ次医療が欠かせないと話す。
「そもそも人の幸せとは何だろうか。
僕は、好きな人と好きな場所で暮らすことだと思う。
それを中心になって支えるのは、医師というより看護と介護。
保健師、訪問看護師と介護職の連携が必須。
医療と福祉の垣根を取り払い、チームで取り組むべきでしょう。
特権化した高度医療志向の医師たちを、
チームで担う地域医療に振り向けるような政策を期待したい」
(編集委員 浅川澄一)
いろひら・てつろう
医師。1960年横浜市生まれ。東大工学部を中退、世界を放浪。
83年京大医学部入学、90年卒業。96年JA長野厚生連に入り、
長野県南牧村の診療所長、98年同県南相木村診療所長。
2008年4月佐久総合病院地域ケア科に移り、現在同科医長。
著書に「大往生の条件」「源流の発想」など。
シニア記者がつくるこころのページ (毎週木曜に掲載)
Posted by ヨクナル at 18:28│Comments(0)
│■ 介護ゼロ・システム
※会員のみコメントを受け付けております、ログインが必要です。