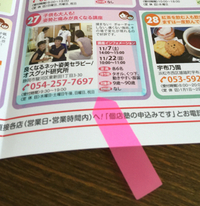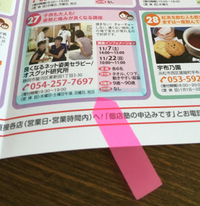2011年11月18日
戈術

郷土の歴史書
著者の浅羽克典さんとあるところでお会いして、なるほど....理解がすすみました。
それは以前より、井川や東河内などに住んでいる方より武田の落武者などの話を聞いていたことがあったからです。
小笠原金左衛門長春の記述は興味をひきます。
時代は1590年(天正18年)
高天神城(鶴翁山)の話がでるのです。
詳しいことが知りたいひとはここをクリック
詳しい話はすごーく、大幅に省くとして、
世は戦国時代で、武田勢との戦で高天神城に関して、
小笠原金左衛門長春の兄、小笠原長忠が、徳川家康によって命を絶たれる。
弟の小笠原長春は生き延びて、ほとぼりが冷めるまで、明(いまの中国)へ渡り、劉邦(漢の統一した関係者といえる人)の末裔の張良という人から「戈術」を皆伝の域に達したそうです。
長春は帰国するのですが、世は徳川の時代になっていて江戸で門弟を(3千人以上)とっていたそうです。
門弟・・・無住心剣流 開祖針ケ谷夕雲
新陰直心流 開祖神谷文左衛門真光伝心斎
真新影流 開祖小笠原源信斎=小笠原金左衛門長春
戈術(ほこじゅつ)
この意味を知り、武術の開祖の真髄に触れた気がしました。
ニコニコの引用先から.......
「武」は、「戈(ほこ)」と「止」をあわせたもの(会意文字)である。
説1
「武術の武という文字は『戈(ほこ)』を『止』めると書いて武となる。つまり武術とは争いを止めることを目的としたもので争うことを目的としたものではない。」という説
説2
「『武』と言う漢字は『戈』を持って歩くさまを表したものである」という見解が一般的
わたしは、戈術は「抑止力」だとおもうですよ。
戦わずして勝つ。